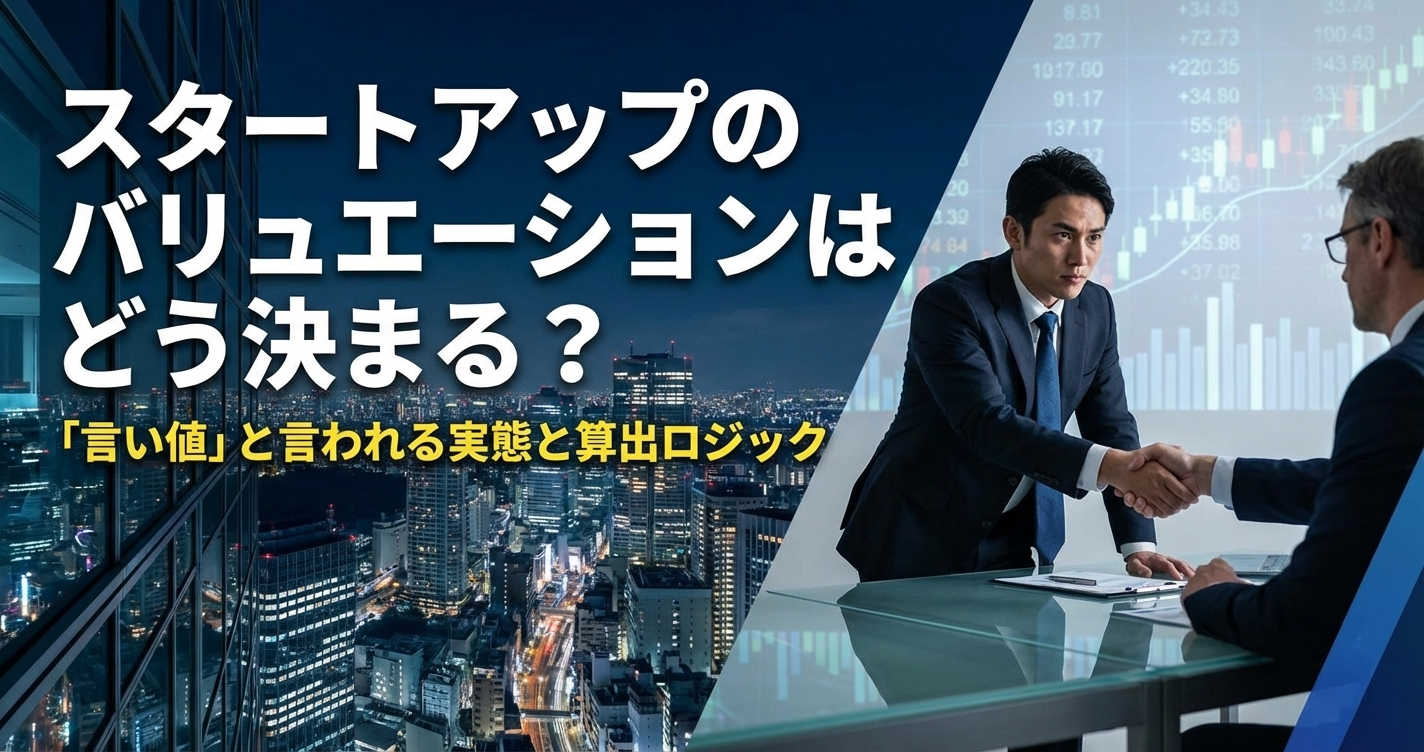マインド
2025.07.08
【保存版】やる気ゼロの部下が動き出す!成功企業が実践する「小さな成功」マネジメント法
S&K Holdings
「何をしても部下のやる気が上がらない」「自分ばかりが空回りしている」そんな悩みを抱えるマネージャー・リーダーの方へ。
実は、部下のモチベーションが低いのには“明確な理由”があるんです。
カギは、“小さな成功体験をどう設計するか”。
本記事では、GoogleやNetflixなどの成功企業が実践している「やる気の科学的アプローチ」を徹底解説します。
この記事はVoicyの「No. 326 モチベーションは小さな成功の積み重ねで作る」を基に執筆しています。
なぜ成長企業ほど社員のモチベーションが下がるのか?「実感の欠如」の正体

どんなに優れたビジョンがあっても、日々の業務にやる気を感じられない瞬間は誰にでも訪れます。その理由の多くは、「自分が前進している実感がないこと」にあります。特に起業直後や成長途上の企業では、目の前のタスクが膨大でゴールが遠く感じられがち。そんなときに求められるのが、小さな成功体験の積み重ねです。
小さな成功とは、必ずしも成果の大きさではありません。達成の手応えや、他者からの承認といった「感情を動かす体験」こそが、やる気の火種になるのです。
なぜ「成果の見える化」が部下のモチベーション向上に効果的なのか?

例えば、営業職のメンバーが大口案件の進捗に伸び悩んでいるとします。そのようなときは、確度の高い小規模案件のクロージングに集中してもらうことで、「決めた」という手応えを得られます。
エンジニアであれば、機能単位のリリースを事例発表してもらうなど、成果を“見える化”して共有する機会を設けることで自己肯定感が高まります。事務職であれば、日常業務の自動化や効率改善など、業務改善に関わる小さなタスクを与えることが効果的です。
こうした設計を行う際のポイントは、「成果が生まれるまでのスパンを短くし、達成の実感をすぐに得られる構造にすること」です。
成功する企業の陰には、意図された「小さな成功体験」がある

GoogleやNetflixといったグローバル企業も、社員の自律性を高めるマネジメントの核に「小さな成功体験」の設計を組み込んでいます。
Googleの「20%ルール」やNetflixの「自由と責任の文化」は、裁量を与えることで自ら達成感をつかませ、やる気の好循環を生み出しています。
「人は命令では動かない」「感情が動いたときに初めて力を発揮する」
この原理原則を活かして成功の芽を日常に意図的に仕込むことが、マネジメントの核心になってきているのです。
【マネジメントの新常識】モチベーションを”与える”のではなく”育てる”場づくり術

マネージャーが「どうすれば部下のモチベーションが上がるか」と悩むのは自然なことですが、実はモチベーションを“与える”ことはできません。できるのは、本人が自ら湧き上がらせるような“場づくり”です。
そのために必要なのが、小さな成功を仕組みとして組み込むこと。最初は半ば強引にでも成功体験を演出し、それが本人の自信や達成感となって定着していく。そうしたサイクルを、日々の業務設計に落とし込むのです。
まとめ:やる気のない部下を変える魔法の一手【小さな成功が大きな飛躍を生む法則】

今回のまとめです。
- 部下のやる気がない原因は「前進の実感の欠如」
- 小さな成功体験=感情が動く“納得の達成”を意図的に作る
- 成果の見える化で自己肯定感が上がる
- モチベーションは与えるものではなく、育てる「場」が必要
- Google、Netflixも実践する「やる気の循環」マネジメント
まずは一歩踏み出せる“簡単な成功”を、部下にプレゼントしてみましょう。
ワンポイント英語スラング:Jock
今日のスラングは「Jock」。これは主にアメリカの学生文化で使われる言葉で、運動部に所属しスポーツが得意な学生を指します。たとえば、「She was a total jock in high school(彼女は高校時代、バリバリのスポーツウーマンだった)」のように使います。単なる“体育会系”というより、ポジティブなニュアンスを含んだ“アクティブで人気者”のイメージです。