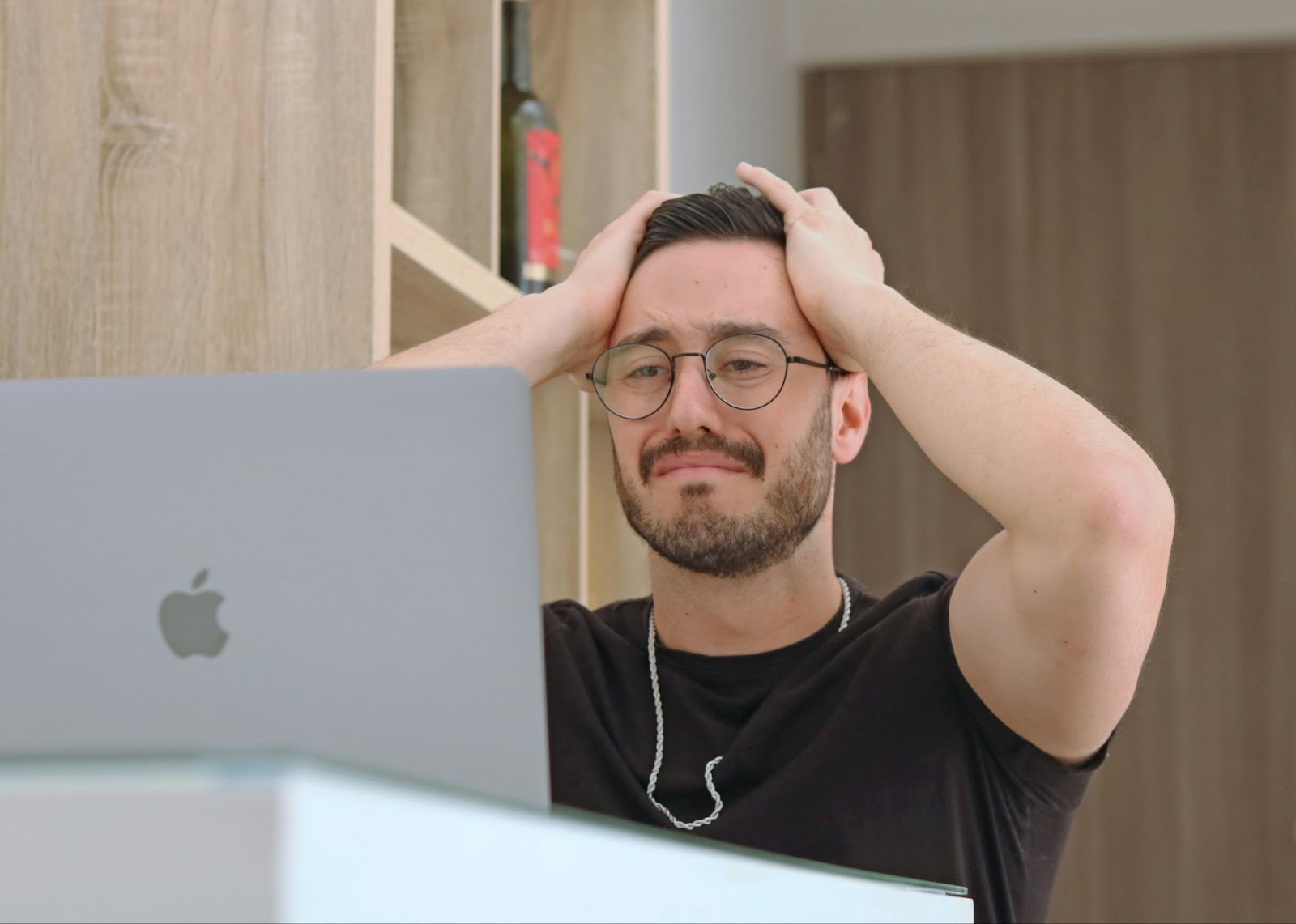
マインド
2025.08.29
【データの罠】なぜ9割の経営者が「因果関係」と「相関関係」を間違えるのか?
S&K Holdings
「この数字、売上に効いてるぞ」──そう思って判断した施策、本当に正しかったのでしょうか?
いま、多くの経営者がデータ分析を武器にしようとしています。
しかし、その裏にひそむ最大のリスクが、「因果関係」と「相関関係」の混同です。
数字に強いはずのビジネスリーダーでさえ、ここでつまずけば成果は真逆に。
“数字が語る嘘”に気づけなければ、あなたの意思決定はすでに間違っているかもしれません。
この記事はVoicyの『No.332 因果関係と相関関係を間違えるな』を基に執筆しています。
間違えると会社が傾く!因果関係と相関関係の本当の違い

まず整理しておきたいのが、両者の定義です。
- 因果関係:ある事象が、別の事象に直接的な影響を与える関係
- 相関関係:2つの事象の間に、同時に変化する傾向が見られる関係(ただし、片方がもう片方の原因とは限らない)
ビジネスでよくあるのが、「相関関係を因果関係と勘違いしてしまう」ことです。これが誤った戦略や無駄な投資につながる原因になります。
【営業の常識を疑え】なぜ「訪問回数を増やせば受注率アップ」は間違いなのか?
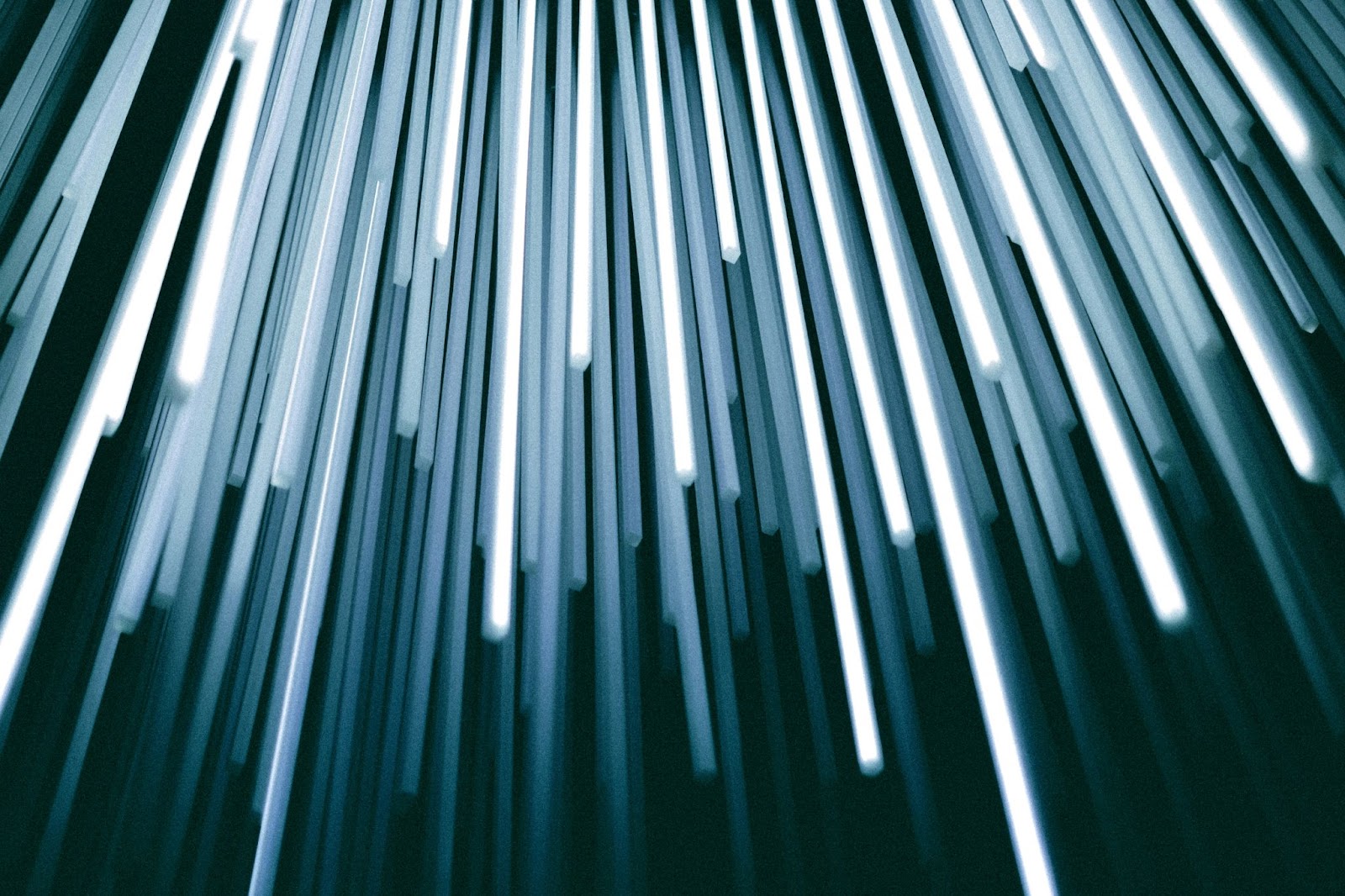
ある企業で、営業マンのデータを分析したところ「訪問回数が多い人ほど受注率が高い」という傾向が見つかりました。これだけを見ると、「もっと訪問すれば受注が増える」と考えるのは自然な流れです。
しかし実態は逆でした。実際には「受注の可能性が高い案件ほど、詰めの対応が必要になるため、訪問回数が増える」だけだったのです。つまり、受注が先にあり、訪問はそのための結果であって原因ではなかったのです。
このように、因果が逆になっているケースは意外に多く、表面的なデータ分析では見抜けないこともあります。
【広告投資の落とし穴】なぜ広告費を増やしても売上が伸びない企業があるのか?

「広告宣伝費と売上には相関がある」として、大きな広告予算を投下する企業もあります。たしかに、成功事例も多いのは事実です。
しかし、注意すべきは「売上が先に増えたことで、広告費に回せる余裕が生まれた」というケース。広告によって売上が伸びたのではなく、売上が好調だったから広告を増やしたという流れです。
広告の効果を正しく測るには、A/Bテストや時系列での比較分析など、より精密な因果検証が必要です。
シンプルな解釈が失敗を招く!データ分析で陥りがちな思考パターン
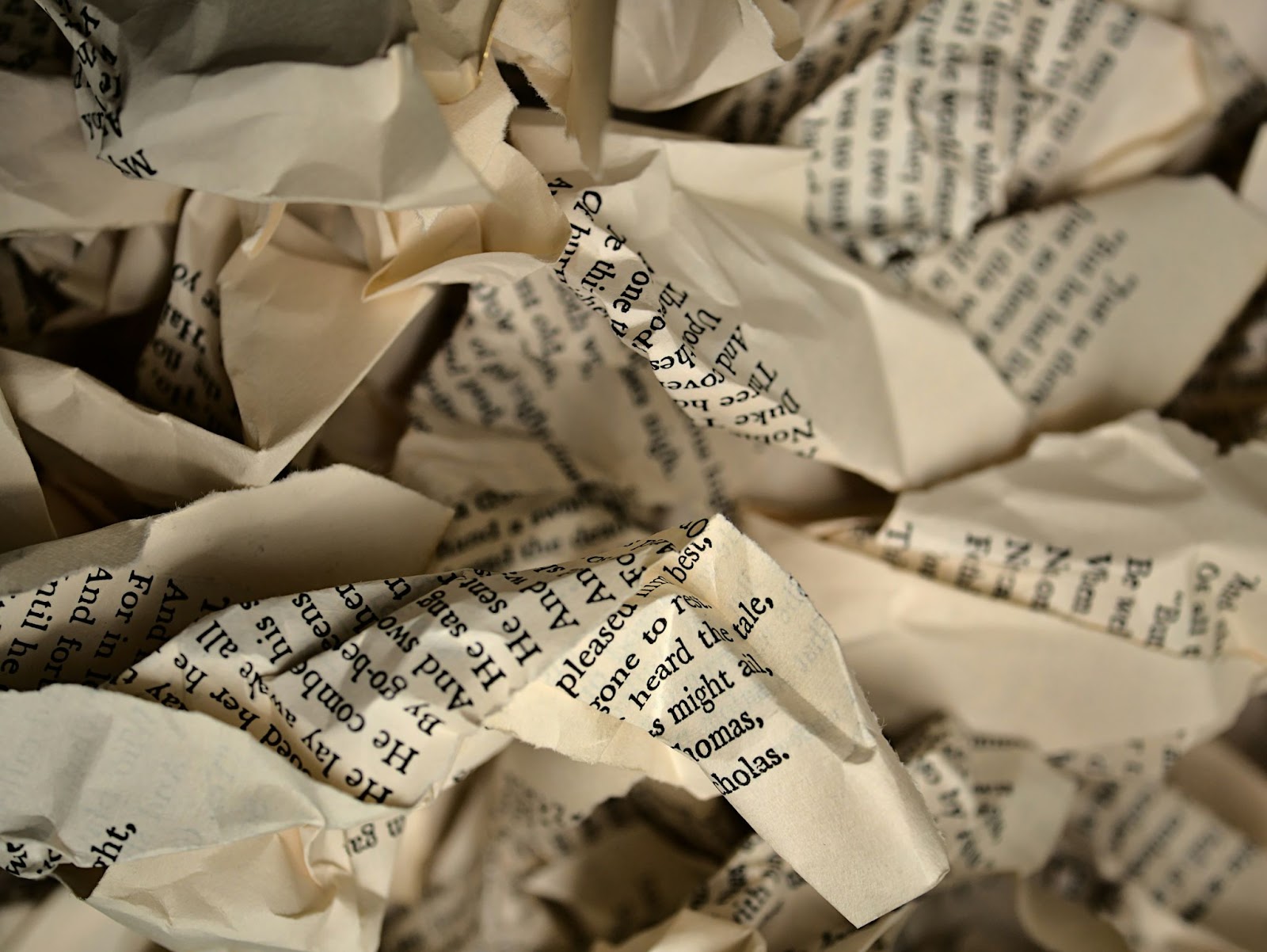
人は「単純で分かりやすい因果関係」を好む傾向があります。たとえば、「雨が降ったから売上が下がった」「残業時間が増えたから生産性が下がった」といった説明は、簡潔で納得しやすいものです。
しかし、その裏には別の要因が潜んでいることもあります。多くの失敗は、「シンプルな解釈」に飛びついてしまった結果なのです。だからこそ、直感ではなく、ロジックで判断することが求められます。
これからのビジネスにおいて必要なのは、「数字を鵜呑みにしない力」です。特に経営者やマネージャー層は、データに基づいて行動する一方で、その背景にある構造を理解しなければなりません。
相関を見つけたら、それが本当に因果かどうかを検証する。複数の視点で事象を捉え、仮説と検証を繰り返す。その積み重ねが、再現性のある成果を導くのです。
まとめ:短絡的な判断がビジネスを狂わせる
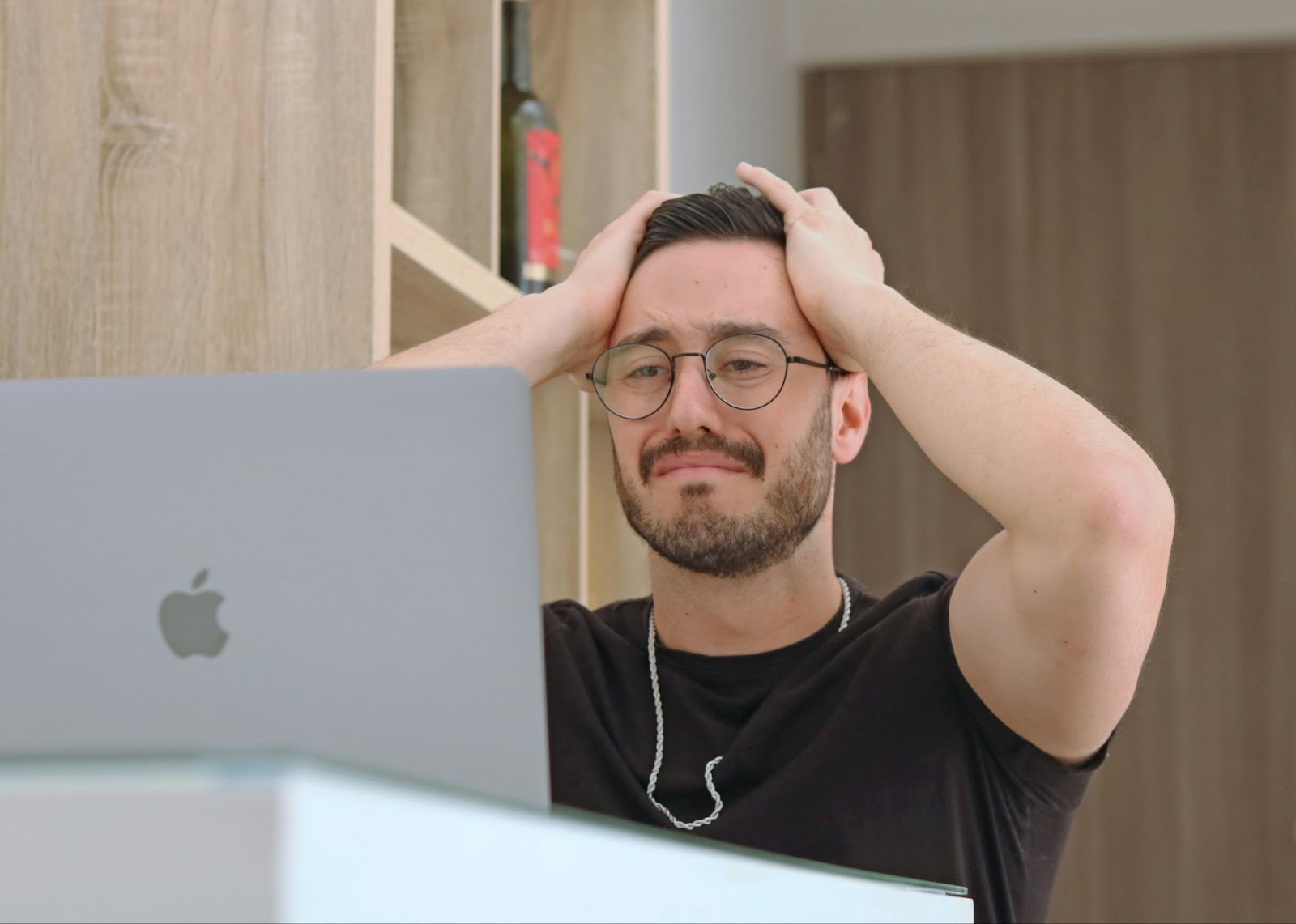
相関関係を因果関係と取り違えると、努力の方向性がズレてしまい、本来得られるはずだった成果を逃してしまいます。重要なのは、「本当にその施策が結果を生んでいるのか?」を問い続ける姿勢です。
少し立ち止まって見直すだけで、正しい判断につながる場面は意外と多いものです。表面的なデータに惑わされず、構造的な因果を見極める力を身につけていきましょう。
ワンポイント英語スラング:in a nutshell
「in a nutshell」は「要するに」「ひと言でまとめると」という意味で使われます。たとえば、「Here’s the idea in a nutshell(要するに、こういうことです)」のように、話を簡潔にまとめる場面で重宝します。ビジネスでも日常会話でも頻出の表現です。



